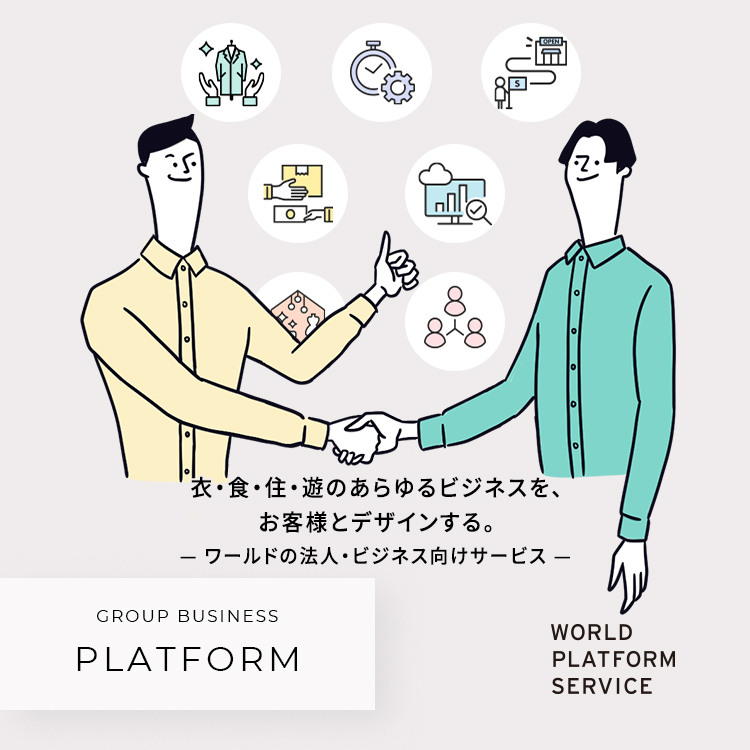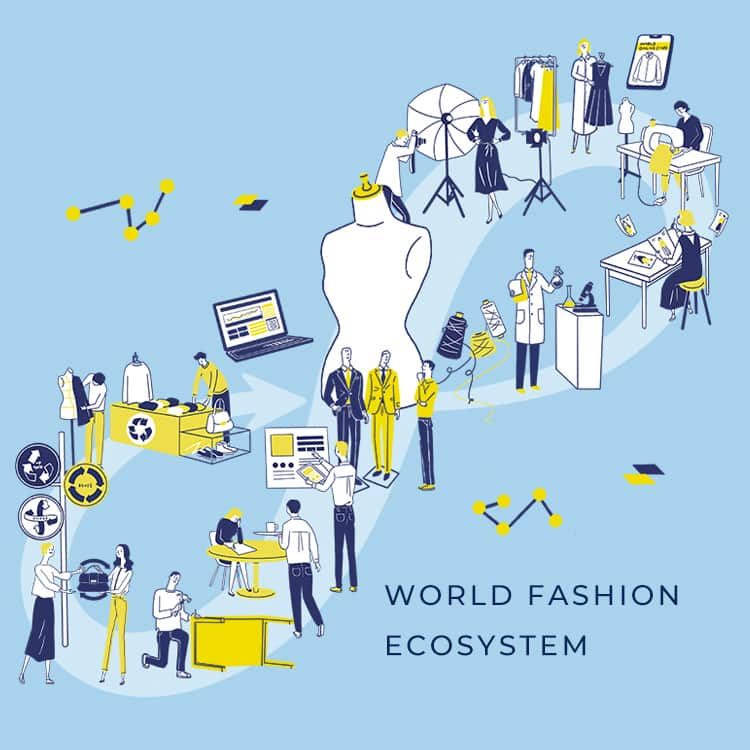NEWS
ニュース
SERVICE
サービス
ワールドグループは、3つの事業を柱に、
ファッションビジネスを創造する「価値創造企業グループ」です
SUSTAINABILITY サスティナビリティ ワールドグループは、ファッションを通じて持続可能な社会の実現を目指します。
-
 Environment 環境
Environment 環境 -
 Social Activities 社会
Social Activities 社会 -
 Governance ガバナンス
Governance ガバナンス